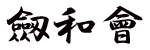居合道の稽古では、無外流居合兵道の教えに基づき、段階的に身体と精神を鍛えていきます。初心者の方でも無理なく取り組めるよう、ひとつひとつの動作を丁寧に学んでいく稽古環境を整えています。
稽古の流れ
素振り
すべての基本となるのが「素振り」です。まずは身体を慣らし、正しい構えと動きを身につけるところから始まります。
短杖の素振り
片手で短い杖を振ることで、刀の操作に必要な左腕を主とした動き方や長い武具の扱いに慣れていきます。
鍛錬棒の素振り
やや重い棒を使うことで、力みに頼らず安定した腰の運用や、ぶれない体幹を意識します。姿勢を保ち続ける集中力も養われます。
模擬刀での素振り
刀で素振りをすることで刃筋を通す動きを身に付けます。動きの連動や間合いの感覚を体感します。これが後の形稽古や抜き打ちにつながっていきます。
抜き打ち
居合の特徴である「抜きながら斬る」動作を習得していきます。形稽古に入る前段階として、基本の斬り方を何度も繰り返し身体で正しい動きを覚えます。
- 横一文字・逆袈裟:腰や重心移動を使い、身体全体で斬ることを覚えます。素早さよりも、丁寧な軌道と安定した姿勢が大切です。
- 真向への斬り:相手の正面をまっすぐ斬り下ろす基本の一太刀。呼吸、姿勢、視線など、心身の整えが求められます。
形稽古


無外流に伝わる形を繰り返し稽古します。形とは単なる振り付けではなく、攻防の理合と精神性が込められた“武術の形”です。
- 一つひとつの形に込められた意図や意味を学びます
- 反復を通して、無理のない自然な動きと“間”を体得します
- 心を整え、集中力を高めることで所作に品が生まれます
形の稽古は、自己との対話でもあります。
段位について
劔和會では、技量の段階を表す昇級・昇段の機会を設けています。
まずは、三級を取得し二級、一級と進み、初段、二段、三段…と昇段していきます。
決して、段位が上だからといって偉いといった物ではございません。習ったとおり素直に稽古していれば誰しもが上達できるというのが先人からの教えです。段位はひとつの区切りであり目的ではありません。何よりも大切なのは、稽古を通して身心が整い技と心が磨かれていく過程です。
また、一定の修行を経ると「免許」「免許皆伝」などの巻物が授与され、伝統的な流派の継承の証となります。
会員インタビュー
稽古の雰囲気や会員さんの声は会員インタビューの記事でご覧いただけます。